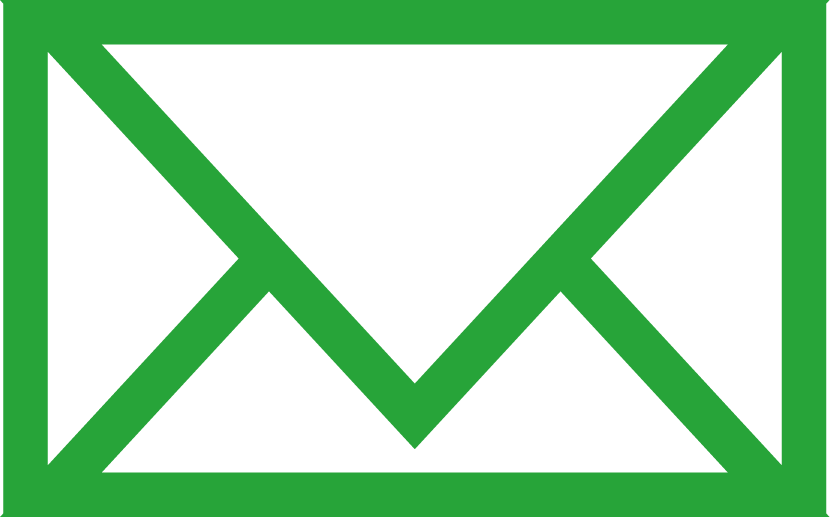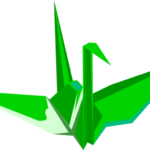【雑記】モンティ・ホール問題とMBAのMECEの考え方に関する考察
1.モンティ・ホール問題とは 今回は弁理士や知財に全く関係ない趣味に近い話しです。 モンティ・ホール問題というのをご存知でしょうか? 数学の条件付き確率の問題の一種ですが、前提条件を多く設定することにより難解なものとした […]
【雑記】弁理士の年収について
1.弁理士の年収と働き方 結論から入りますが、弁理士の年収についてですが、中堅の雇われ弁理士で600万~700万(年齢30代くらい)くらいが妥当なようです。 最近は、特許事務所もあまり儲かっていないので、特許事務所より企 […]
【雑記】比較対象の選択により特定事象の良し悪しが決まる
1.課題(比較すること)人は「比較」を行うことにより物事の良し悪しを決定することを幼少期から叩き込まれます。例えば、テストの点数ですとか、試験、隣の芝が青く見える、など枚挙にいとまがありません。実際問題としては、「比較」 […]
【雑記】売上数千万~数億あるとクレカキックバックがある
1.課題(売上はたくさんあっても営業利益が少ない)売上だけみると数千万~数億の稼ぎがある、というのは中小企業によくあることです。一般的にみると凄そうですが、経費(人件費、材料費、インフラ費など)がたくさんあると、残りの営 […]