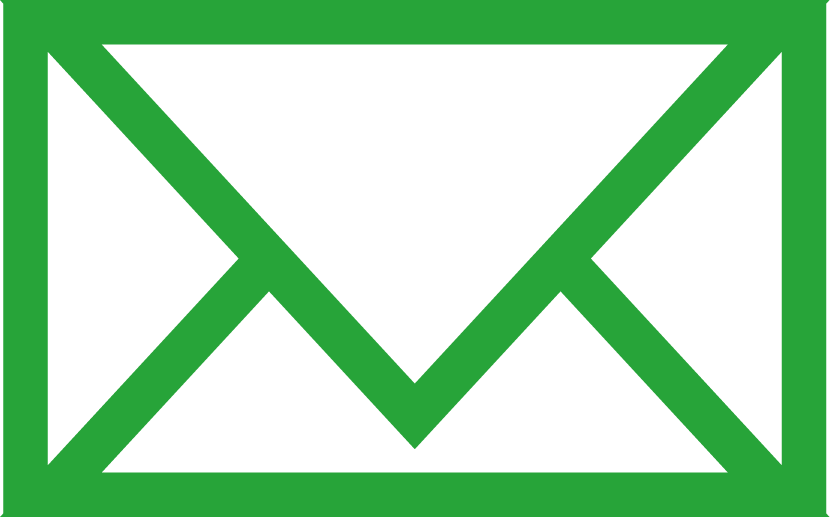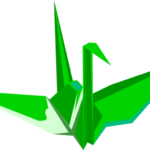【欧州特許】Partial ESR (部分ESR)への対処方法
1.課題(Partial ESR)欧州特許庁(EPO)に特許出願すると、Partial ESRというものをもらうことがあります。内容は、発明の単一性違反に関するものでして、複数の発明、つまり、複数の請求項のまとまり(グル […]
【仕事の効率化方法5】書類作成でミスを無くす方法
1.課題(作成した書類に誤植がある)書類作成において、誤記や誤植、いわゆるミスはつきものです。人間だから、ミスがあって当たり前なのですが、ビジネスの世界では許されないことも多々あります。そこで作成した書類から可能な限り誤 […]
【仕事の効率化方法4】口頭の内容は書面化する
1.課題(口約束でもめる)客先との仕事の打ち合わせや電話では、書類を介さずに口頭で指示を受けることがあります。このような場合、お客様の指示のもと書類や納品物を作成したにもかかわらず「そんな指示はしていない」とか、「全くの […]
【仕事の効率化方法3】書類を最速で仕上げる方法
1.課題(書類を最速で仕上げたい)社内資料やお客様への発表資料の作成は、社会人が逃れることのできないものの一つです。可能な限り早く仕上げて、余った時間を別の仕事や余暇にあてたいですよね。しかしながら、書類作成に時間がかか […]
【仕事の効率化方法2】紙資料でなく電子データをもらう
1.課題(紙の資料からパワポ等を作成することの非効率さ)お客様から頂戴した資料に基づいて、パワポやらワードやらの文章を作ることがよくあります。しかしながら、この資料が紙媒体である場合には、それを手打ちするというのは非効率 […]
【仕事の効率化方法1】山積みの仕事への対処方法
1.課題(山積みの仕事)特許事務所では、たくさんの案件ファイルを扱います。その案件ファイル毎に作業量と困難さの「重さ」は異なります。そのため、「重い」案件からこなしていくといつまで経っても、他の案件ファイルが無くならない […]
【お知らせ】おりがみ国際特許事務所を開業しました
おりがみ国際特許事務所を開業しました 2021年9月1日付でおりがみ国際特許事務所を開業しました。 弊所では、知財に関するコンサルや教育、化学・機械分野の特許業務全般、商標業務全般、外国出願全般( […]
特許権は事業に必要?弁理士が回答します
特許権は事業に必要?弁理士が回答します 本記事は、おりがみ国際特許事務所が執筆したものです。今回は、特許権の必要性について分かり易く解説します。この記事の要点①.特許権の効力が分かります。②.特許権を取得す […]