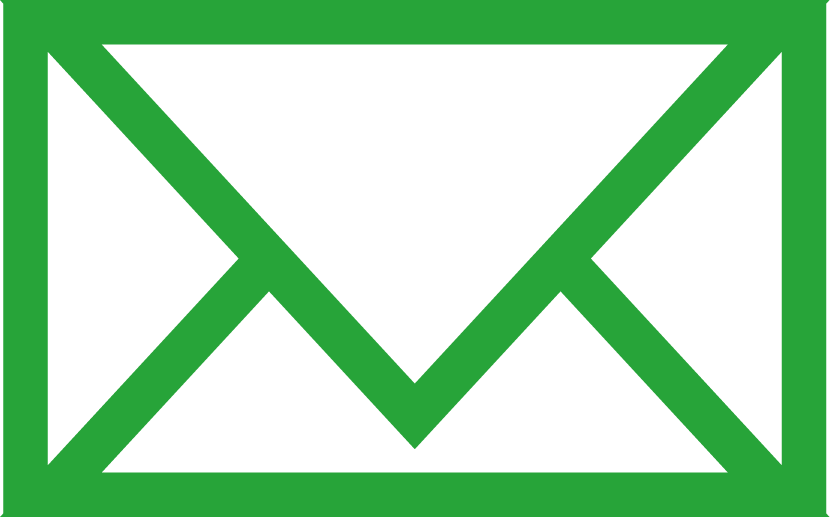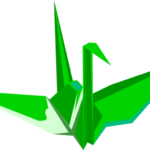【特許】国際出願の国内移行に関する願番の取扱
1.国際出願の国内移行に関する願番の取扱 国際出願の国内移行では、国内書面という書類に国際出願番号(PCT/US20XX/XXXXXX)を記載します。 すると、実務上は、国内書面の提出後に、国内用の願番通知が届き、以降は […]
【特許】外国語国際出願や外国語書面出願の翻訳文等の補正開始時期について
1.外国語特許出願や外国語書面出願の翻訳文 外国語特許出願(外国語のPCT国際出願)の国内移行や、外国語書面出願では、原則としてその翻訳文(明細書、特許請求の範囲、要約、図面)の提出が追加で発生します。 なお、外国語特許 […]
【特許】国際出願翻訳文提出特例期間や外国語書面の日本語翻訳文の提出期限等の期限備忘録
1.国際出願翻訳文提出特例期間や外国語書面の日本語翻訳文の提出期限等の期限備忘録 タイトルどおり、実務者向け備忘録です。 本件、2023年6月9日付における情報ですので、法改正等により変わる可能性があることに注意ください […]
【システム】Intel(r) Iris(r) Xe Graphicsドライバ更新での文字崩れ対処
1.GPU使用率100%でフリーズ 今回は雑記っぽい話しです。 ラップトップ(ノートPC)で使用しているGPUとして、Intel(r) Iris(r) Xe Graphicsをメインに使用しているんですが、あるときから「 […]
【特許】補正書での「補正により増加する請求項の数」記載判断について
1.手続補正書の記載 請求項数が増加した手続補正書を作成しているときに「【補正により増加する請求項の数】」の項目を作るかどうか判断に迷うときがあります。 実務者が迷うマイナー問題ですが、結構重要なのでメモがてら書いておき […]
【特許】優先権期限徒過した外国語特許出願(国際出願)の優先権回復の根拠条文等について
1.優先権とは ※今回の記事は、弁理士受験生や実務者を想定したものです。勉強や知識の再確認にお役立ていただければと思います。 日本の特許法では先願主義(簡単に言うと早い者勝ち)を採用しているために、特許出願は可能な限り早 […]
【知財事務】発信主義又は到達主義が適用される書類の範囲を説明します
1.特許庁が書類を受領したとみなす日時 特許庁は、書類によって発信主義と到達主義を使い分けています。 発信主義とは、簡単に言うと郵便物等の通信日付印の日付で受領したとみなす主義のことです。 また、到達主義とは、特許庁が実 […]
【商標】商標権を早期・迅速に取得する方法
1.商標登録とは 商標登録とは、商標(商品及び/又はサービスに表示等するもの)を、特許庁に対して登録し、商標権を取得する一連の流れを意味します。 実際に特許庁に対して登録するためには、登録を所望する商標と、その商標と共に […]
【特許】第4回 簡単に分かる拒絶理由の対処方法(審査官の指摘が不当な場合:新規性)
1.前回のおさらい 簡単に分かる拒絶理由の対処方法シリーズは、初心者向けの拒絶理由通知の対処方法を示しています。 もちろん実務家の方も頭の整理として参照いただけますと嬉しいです。 さて、おさらいですが、第1回では、特許庁 […]
【特許】第3回 簡単に分かる拒絶理由の対処方法(審査官の指摘の妥当性・失当性の確認))
1.前回のおさらい 前回(第2回)では、特許庁から通知される拒絶理由の解消において場合分け(パターン化)することで機械的に対処することができることを示し、特に、パターン化の最初のフローのうち、拒絶理由(事例)を当てはめる […]